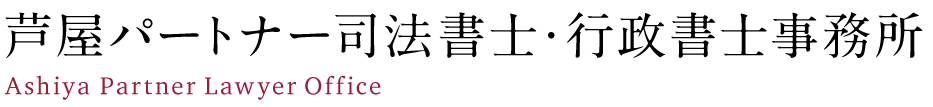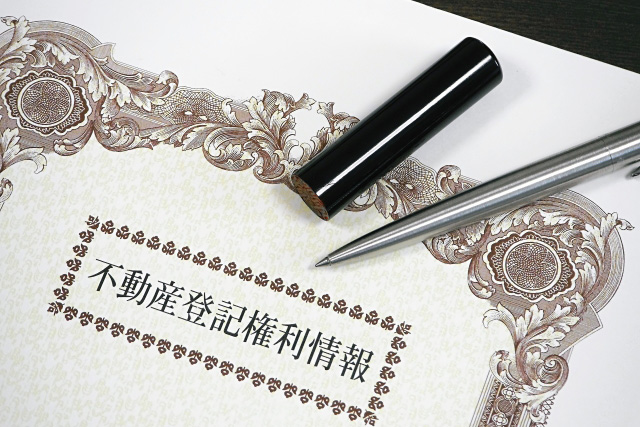相続放棄には期限があります。民法ではこのように定められています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
(民法915条1項)
3ヶ月を経過すると単純承認したことになり、原則相続放棄が認められないこととなってしまいます。そのため相続放棄は早めに検討し手続きを行わなければなりません。
3か月を経過すると相続放棄はできないのか
相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月にしなければなりませんが、熟慮期間の3ヶ月を経過したときでも特別の事情がある場合は相続放棄が認められることがあります。
特別な事情とは、以下のような場合となります。
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。
(最高裁判所昭和59年4月27日)
上記のように相続財産があることを認識していなかった場合以外でも相続人が被相続人の亡くなったことを知らなかったような場合も相続放棄が認めれる可能性があります。
熟慮期間の伸長の申立て
相続放棄の熟慮期間の伸長は家庭裁判所に対して申立てることにより認められ、相続財産の全ての調査・把握が3カ月では間に合わないような場合に行います。
熟慮期間の伸長の申立期間は、自己のために相続の開始があったこと知った時から3カ月以内(熟慮期間中)に伸長しなければなりません。
相続放棄申立て前の注意点
熟慮期間経過以外にも単純承認したものとして扱われてしまう法定単純承認というものがあります。相続放棄の申立ての前に遺産を処分に当たる行為をしたり、隠したりしたような場合です。
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない
2 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
3 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。(民法921条)
このような場合はご相談ください
●無用な相続争いに巻き込まれたくない
●相続人の一人に相続財産を集中させたい
●マイナスの財産(借金)の方が多いため、放棄したい
●財産が資産価値のない山林ばかりで売却が難しく、引き継ぎたくない
●生前に故人との交流がなく、相続するつもりはない
相続放棄は期限内に家庭裁判所に書類を提出しなければならず、できるだけ早く被相続人の遺産を把握する必要があります。
相続放棄の手続きについては司法書士にご相談ください。