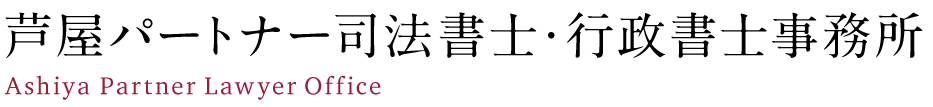被相続人と疎遠の場合や生前に遺言書を残しておくという話をしたことがあるが遺言書が発見されない場合など、遺言書があるか分からないときがあります。
公正証書遺言を作成していた場合でも公証役場から通知されるということもありません。
遺言書があるかどうかは遺産分割手続きにも大きく影響する場合があるため、不明な場合は必要に応じて調査をしておく方がトラブルの防止になります。
遺言調査の方法
遺言調査は以下の方法で行うことができます。(公正証書、自筆証書遺言)
- 公証役場での検索システムの利用
公正証書遺言の検索は公証役場での公正証書遺言の検索システムを利用して確認することができます。
相続人、受遺者、遺言執行者又はそれらの代理人からの請求である必要があります。
検索は最寄りの公証役場へ出向く必要があるため、予め公証役場へ連絡の上、必要書類等を確認して進める方がスムーズです。 - 法務省の自筆証書遺言保管制度での確認
被相続人が自筆証書遺言を法務局での保管制度を利用しているかどうかは、「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することで判明します。
相続人、受遺者、遺言執行者又はそれらの代理人からの請求である必要があります。
請求は管轄内の法務局へ出向くか郵送で手続きを行うことができます。 - 遺品・貸金庫等の探索
被相続人の遺品や金庫、金融機関の貸金庫を探索してみてください。
自筆証書遺言が発見された場合は、家庭裁判所で検認手続きが必要となるため、開封せずに検認手続きを進める必要があります。
遺産分割協議後に遺言書が発見された場合
遺言書があるにも関わらず、ないものと誤認して相続人間で遺産分割協議が成立した場合でもその遺産分割協議は原則は無効となります。
ただし、相続人全員の合意があれば、既になされた遺産分割の結果を有効にすることができ、遺産分割協議をやり直す必要はありません。
しかしながら、相続人全員の合意があっても相続人の範囲や遺産分割の対象が変わる場合には、その合意は無効となることもあるため、注意が必要です。
相続手続きを進める際、遺言書の存在が手続きを大きく左右します。
遺言書の作成や相続手続きは、法律事務の専門家である司法書士へご相談下さい。